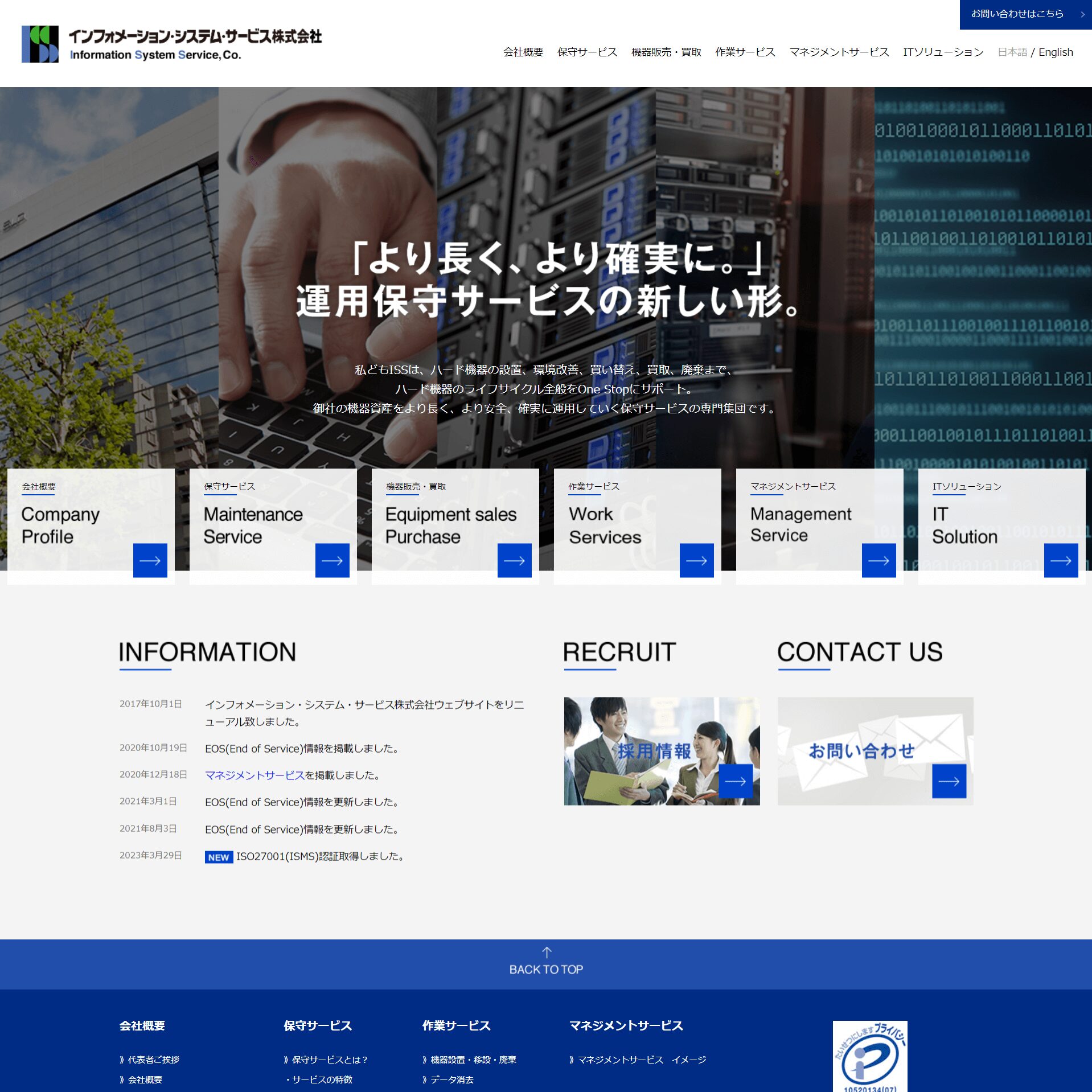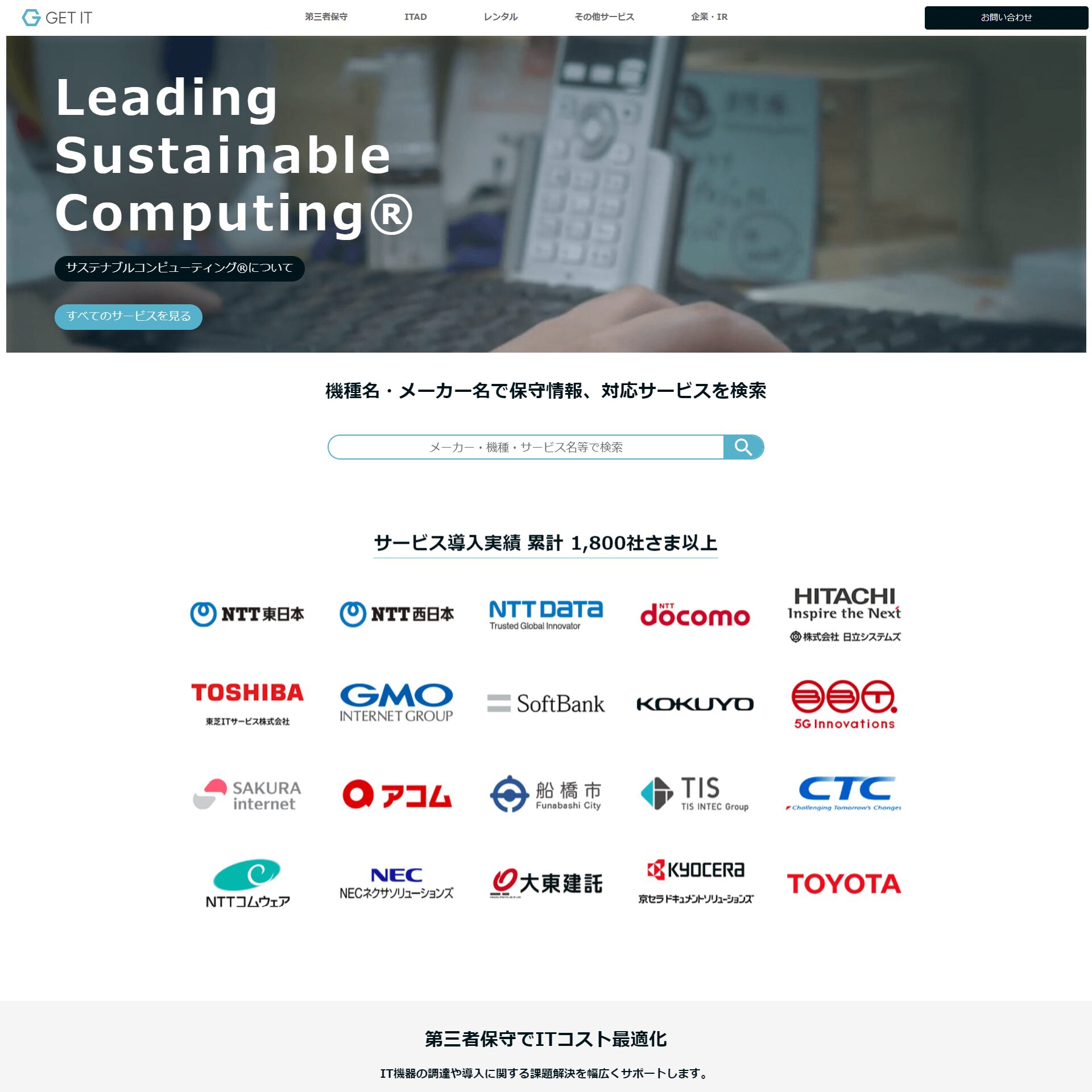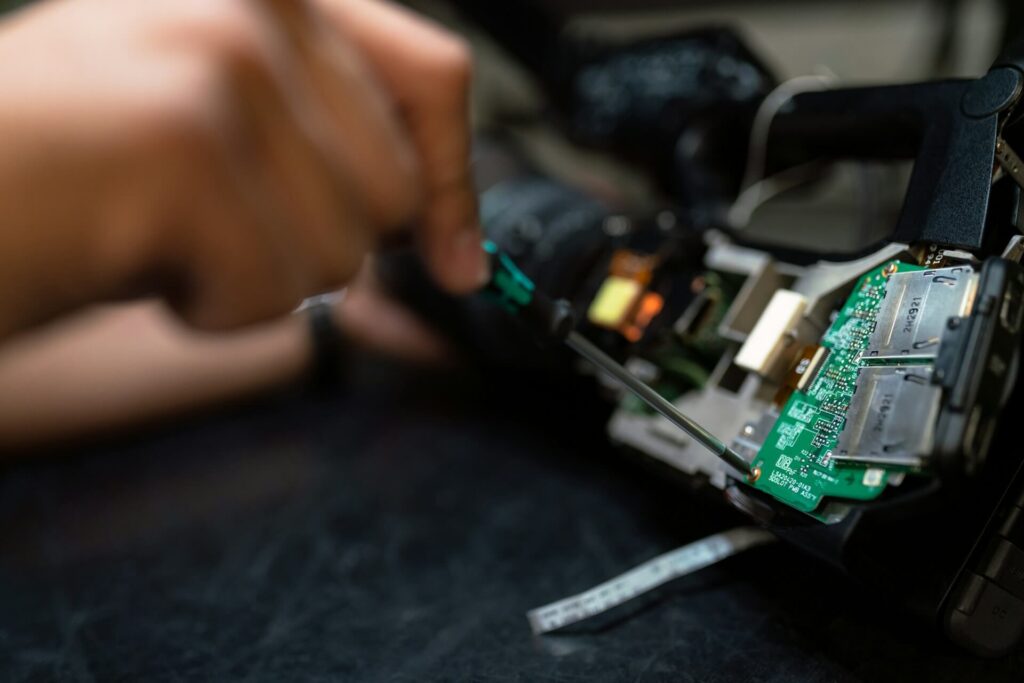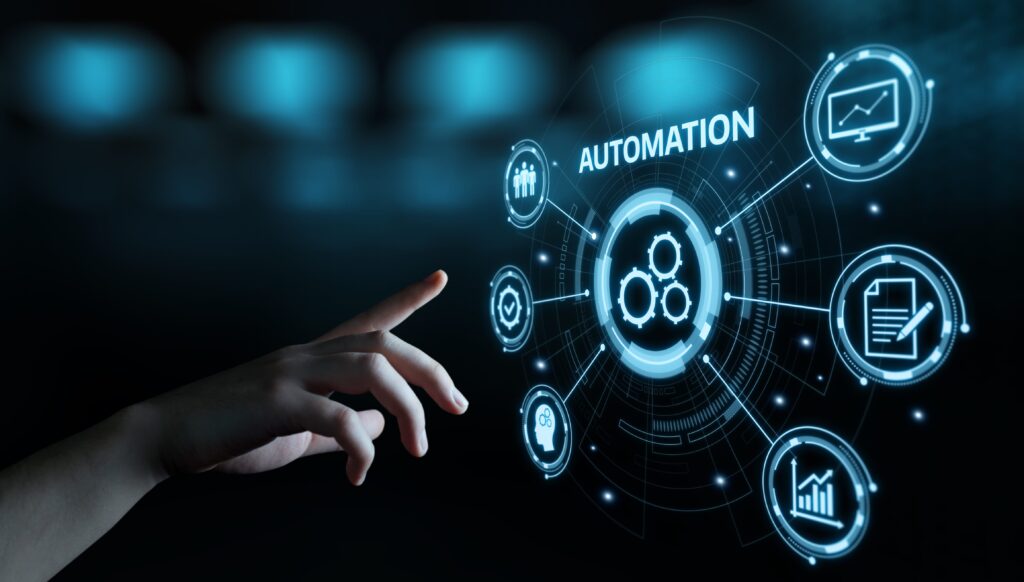自社のIT機器のサービス終了や、維持コストの増加で困っていませんか。第三者保守サービスを利用すれば、そういった悩みをまとめて解決してくれます。本記事では、第三者保守サービスの内容や種類について詳しく解説します。自社での保守に限界を感じている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
第三者保守サービスの内容
第三者保守(EOSL保守)は、メーカーが定めた保守期限(EOSL)を過ぎたIT機器に対し、メーカー以外の専門事業者が提供する延命保守サービスです。対象となるのはサーバーやストレージ、ネットワーク機器など幅広く、オンサイト修理や障害対応を通じて既存機器の安定稼働を支援します。
メーカー純正の保守と異なり、運用実態に合わせた柔軟な契約が可能で、コスト削減や運用効率化につながる点が大きな特徴です。また、異なるメーカー製品をまとめて保守できるため、保守窓口を一本化できます。
また、EOSLを理由に急いで機器更新を行う必要がなく、自社のスケジュールに沿ったシステム移行を実現できる利点もあります。メーカー保守が終了すると、修理部品の入手が難しくなりやすいです。
また、サポート対象外となり高額な修理費が発生するリスクもあります。さらに、ソフトウェアやOSの更新が停止することでセキュリティリスクが高まり、マルウェア感染や不正アクセスの危険性も増大します。
加えて、経年劣化による故障の増加や部品調達難により、業務停止や多額の更新コストが発生するリスクも見逃せません。こうしたリスクを軽減し、サポート終了後も安定した稼働を維持するために、第三者保守サービスが有効な手段として注目されています。
「第三者保守」と「EOSL保守」は似ていますが、厳密には異なるサービスです。前者はメーカー以外の企業が提供する保守サービス全般を指し、後者はその中でも特にメーカーサポート終了後の機器を対象とする保守サービスを意味します。
第三者保守は、ハードウェア修理や部品交換、オンサイト対応、障害時のパーツ送付など多様なサービスを提供可能です。保守部品は国内外のセカンドマーケットから調達し、検品・動作確認を経て管理されることで、長期的な保守体制が整えられています。
さらに、障害受付窓口やスポット保守などの仕組みにより、契約の有無にかかわらず単発対応も可能です。監視サービスや構築支援、データ消去、HDD返却不要、IT資産処分(ITAD)などのオプションも用意され、セキュリティ強化や運用効率化に貢献します。
このように第三者保守は、コスト削減と柔軟な運用を両立しながら、IT機器の延命利用と安定稼働を実現するための有効な選択肢となっています。
第三者保守サービスの種類
ここからは、第三者保守サービスの種類についてみていきましょう。代表的な5タイプの特徴を整理すると次の通りです。
幅広い保守種別に強みのあるタイプ
このタイプは、オンサイト、パーツデリバリー、スポット保守、遠隔監視など多様な保守形態に対応し、カスタマイズ性が高い点が特徴です。ゲットイットのサービスのように、預託保守やリモート通報などを組み合わせ、独自のR&Dで希少機種にも対応できる柔軟性を備えています。
スポット保守に強みのあるタイプ
このタイプは障害発生時のみ短期的に利用でき、コストを抑えたい企業に向いています。業者によっては対応速度や訪問時間帯別のプランを提供しているので、契約不要で単発利用できる柔軟な運用が可能です。
保守パーツの備蓄数に強みを持つタイプ
このタイプは、多機種環境や長期稼働を前提とする企業に最適です。データライブのサービスのように、大規模な備蓄倉庫で数十万点以上の部材を管理し、迅速な部品提供と高い稼働率を支えます。
オンサイト保守をメインとするタイプ
このタイプは、重要システムの安定運用を重視する企業に適しています。ロジネットサービスやエスエーティのように、24時間対応や翌営業日訪問など、緊急度に応じた複数プランが選べるのが特徴です。
故障対応に特化したタイプ
このタイプは、定期契約をせずとも障害時のみ修理やパーツ送付を受けられる仕組みで、短期間・低コストでの延命運用に有効です。NTTデータ カスタマサービスなどが提供しており、全国規模の迅速対応体制が整っています。
第三者保守サービスの注意点
第三者保守サービスは、メーカー保守終了後のIT機器を延命利用する有効な手段ですが、対応範囲には一定の制限があります。主にハードウェア保守に特化しているため、ソフトウェア面のサポートは基本的に対象外です。
まず、OSやアプリケーションのセキュリティ更新や機能追加は提供されず、必要に応じて自社で対応する必要があります。また、ライセンス管理も利用者側の責任となり、再認証や移行作業、ファームウェア設定の引き継ぎなどはサポート外です。
サブスクリプション型ライセンスでは、メーカー側で契約継続ができないケースもあります。さらに、障害発生時の原因切り分けは利用者が行うのが原則で、ソフトウェア起因のトラブルや詳細な原因分析は非対応となる場合があります。
修理後の環境復元やアプリ再設定などもサポート範囲外です。また、自動発報やセキュリティ関連機能など、メーカーのクラウド連携を前提とした機能は利用できなくなることもあります。
こうした制限を踏まえ、自社の運用体制や求める保守範囲を明確にし、最適なサービスを選定することが重要です。
まとめ
メーカー保守が終了した後も、IT機器を安全かつ経済的に使い続ける手段として注目されるのが「第三者保守サービス」です。コスト削減や柔軟な運用を実現できる一方で、オンサイト修理からスポット保守、遠隔監視まで多彩なタイプが存在し、自社の運用環境に最適なプランを選べるのが大きな魅力です。特に、複数メーカー製品をまとめて保守できる点は、保守窓口の一本化や業務効率化にもつながります。ただし、ソフトウェアやライセンス関連は対象外となるケースもあるため、注意点を理解したうえで導入を検討することが大切です。第三者保守を上手に活用することで、コストを抑えつつ、安定したITインフラ運用を長期的に実現できます。