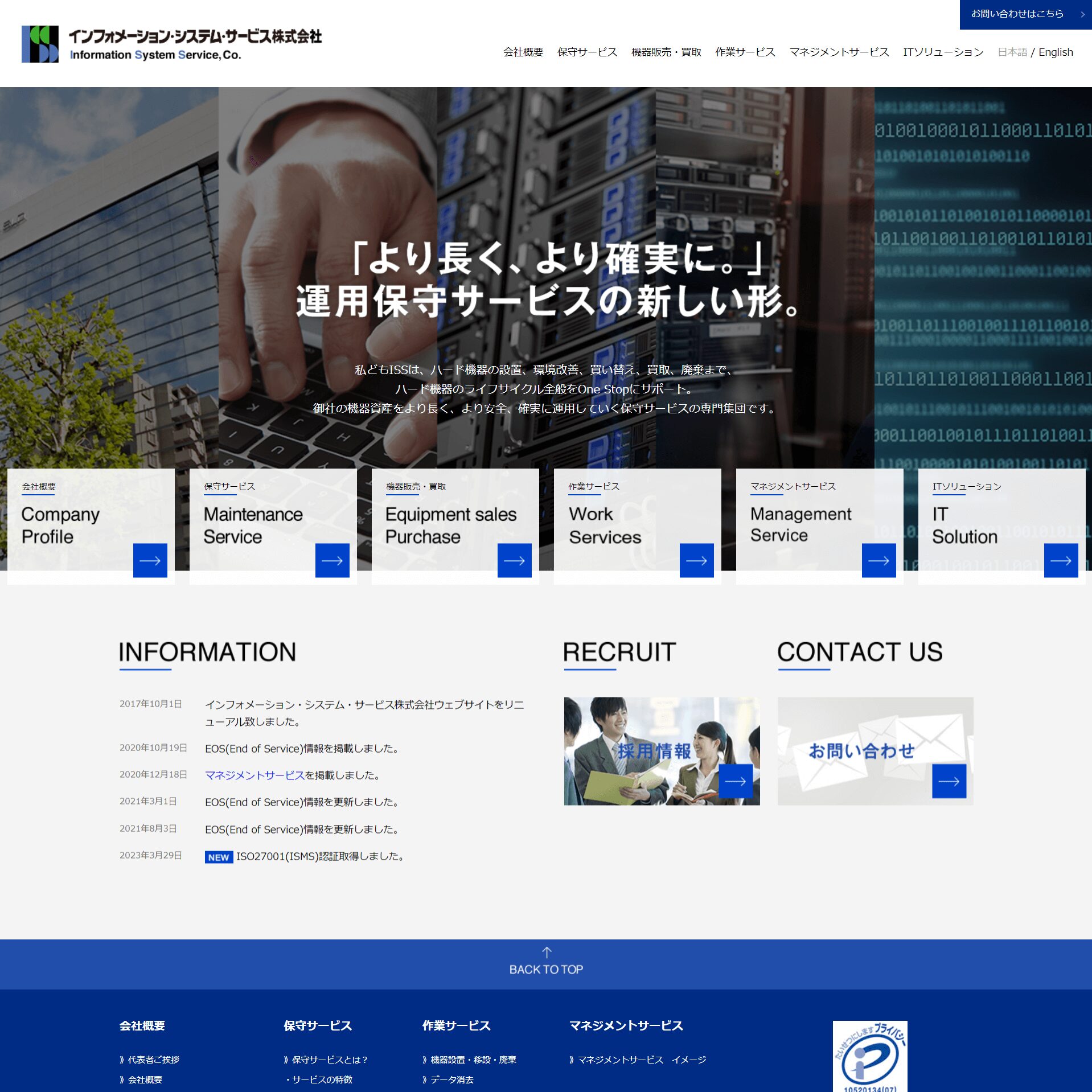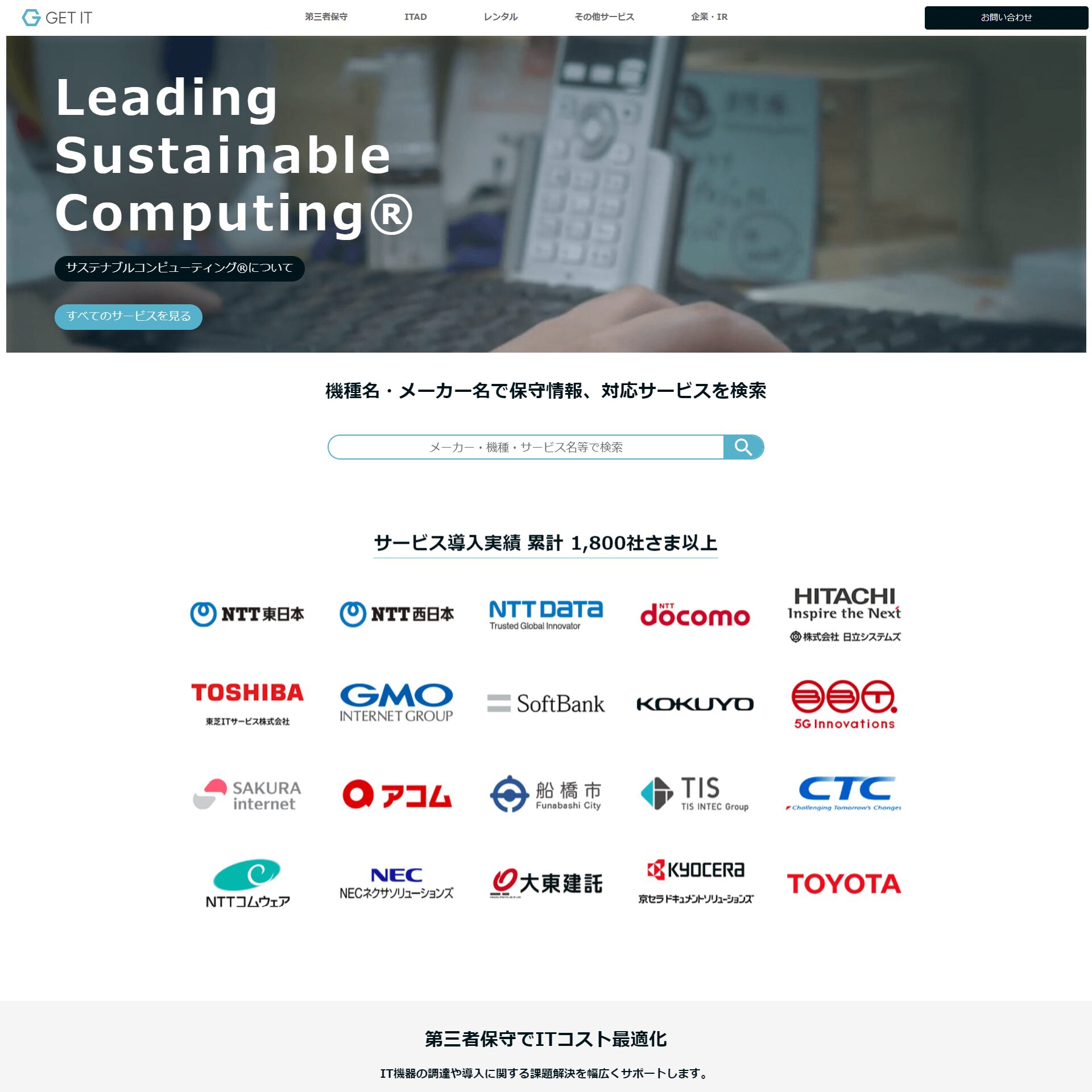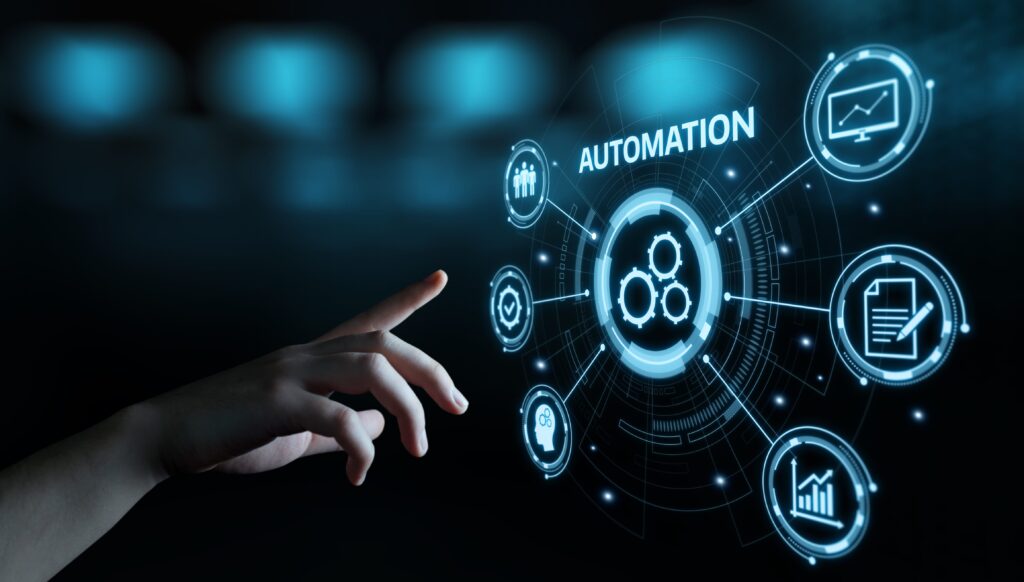企業のITインフラを支えるサーバーは、安定した運用と継続的な保守管理が欠かせません。なかでも「保守期間」は、メーカーや保守業者が修理・部品供給・技術支援などを提供する期間を指し、サーバーの安全運用に直結する重要な指標です。保守期間が過ぎるとメーカーからのサポートが受けられなくなるため、計画的な対応が求められます。この記事では、サーバーの保守期間の基本知識から期間満了後の対応策まで、幅広く解説します。
CONTENTS
サーバー保守とは?
サーバー保守とは、サーバーの安定稼働を維持するために行う点検・管理・修理などの業務全般を指します。企業にとってサーバーは、業務システムやデータベース、メールやファイル共有などを支える基盤であり、その稼働が止まれば業務全体に大きな影響を及ぼします。
主な保守内容として「障害発生時の復旧対応」「ハードウェアの部品交換」「OSやファームウェアのアップデート」「セキュリティパッチの適用」などが挙げられます。とくに、システムに障害が発生した際には、迅速に復旧することでビジネスへの影響を最小限に抑えられます。
サーバーを利用するうえで、サーバー保守作業は欠かせない取り組みのひとつです。
サーバー保守期間とは?
サーバーの保守期間とは、メーカーやベンダーが製品に対してサポートを提供している期間のことを指します。具体的には、故障時の修理対応や部品交換、ファームウェアの更新、セキュリティパッチの提供などを受けられる期間です。
サーバーの保守期間には「ハードウェアの保守期間」と「ソフトウェアの保守期間」の2種類が存在します。ハードウェアでは、部品の供給可能期間に基づいて設定されており、一般的には5〜7年程度が目安です。一方、ソフトウェアについては、開発元が機能追加や脆弱性対応を行う期間であり、こちらも数年でサポートが終了することがあります。
保守期間を過ぎたサーバーは、突発的なトラブル発生時に迅速な対応ができなくなるため、注意が必要です。
なぜ保守期間が設定されているのか
サーバー機器には、購入から一定期間のあいだ、メーカーや保守ベンダーによって修理やサポートを受けられる「保守期間」が設定されています。保守期間が設定されている理由のひとつに「交換用の部品を長期間確保しておくことが難しい」ことが挙げられます。
ハードウェア製品は年月とともに劣化や故障リスクが高まるため、メーカー側も永続的に部品を製造・保管し続けることは現実的ではありません。そのため、保守期間を明示し、一定年数が経過した機器についてはサポートを終了する方針が取られています。
保守期間を超えた機器は、修理対応ができなかったり、部品が入手困難になったりするため、突発的なトラブルに対応しづらくなります。そのため、IT資産を安定運用するには、保守期間の把握と適切な管理が不可欠と言えます。
保守期間が終了すると何が起こるのか
保守期間が終了したサーバーをそのまま使い続けると、さまざまなリスクが生じます。たとえば、メーカーや保守ベンダーによる修理・部品交換・技術的なサポートが受けられなくなります。万が一、故障が発生しても、修理用の部品が手に入らないため、復旧が難しいといったリスクがあります。
また、メーカーは、保守期間を過ぎてから見つかったセキュリティ上の脆弱性には対応してくれません。そのため、サイバー攻撃を受ける可能性が高まります。とくに企業においては、業務システムや顧客情報を扱うケースも多いため、保守切れのサーバーを使い続けることは重大なリスクとなり得ます。
こうしたリスクを未然に防ぐためにも、保守期間が終了する前に代替機に切り替えたり、第三者保守サービスを導入したりといった対策を検討しましょう。
保守期間の確認方法
サーバーを構成する要素ごとに保守期間は異なります。それぞれくわしく解説します。
OS・ミドルウェアの公式サポートページ
OSやミドルウェアの保守期間については、公式サポートページにて確認することができます。たとえば、Microsoft社が提供するサーバー向けOS「Windows server 2016」は、2022年1月11日が標準保守期限として公表されています。2027年1月12日までは、延長サポートが受けられます。
利用しているバージョンがすでにサポート対象外となっている場合、脆弱性対応や技術サポートが受けられないため、早めのアップデートが必要です。使用中のソフトウェアのサポート状況は定期的にチェックすることをおすすめします。
ハードウェアのシリアル番号から確認
サーバー機器には、それぞれ固有のシリアル番号が付与されています。メーカーの公式サイトでは、このシリアル番号を入力することで、保守期限や保守状況を確認できます。
なお、ハードウェアに関しては、OSやソフトウェアのように特定の保守期限は定められていないことがほとんどです。購入後5年間といったように、購入時期に関わらず一定期間サポートが受けられます。
ただし、一部メーカーによっては、特定の日付までの保守期間が設けられているケースもあります。正確な保守期間については、購入時の契約書や規約などを確認してみましょう。
保守期間が終了したらどうすべきか
サーバーの保守期間が終了すると、メーカーやベンダーによる修理対応やセキュリティアップデートなどのサービスが受けられなくなります。放置したままだと、障害が発生した際に迅速な復旧ができず、業務停止や情報漏えいといったリスクが高まります。このような事態を防ぐためには、以下のような対応が考えられます。
延長保守契約の検討
メーカーによっては標準保守期間を超えた機器に対して、延長保守を提供しています。たとえば、通常5年間の保守期間を7年や10年まで延長できるケースもあります。
ただし、延長保守は費用が高額になることが多く、対象機種やサービス内容に制限があるため、事前の確認が欠かせません。なかには、部品供給が終了しているため、延長保守が受けられないこともあるため、早めの対処が必要です。
新器機への入れ替え
導入から年数が経過したサーバーは、性能や省エネ効率が落ちているケースも多く、今後の運用を見据えると入れ替えの検討が現実的です。 新機種に入れ替えることで、最新のセキュリティ対策やサポートが受けられるようになるほか、ハードウェアのトラブルを未然に防ぐことも可能です。
第三者にサポートを依頼する
「コストを抑えながらもサポート体制を維持したい」という場合には、第三者による保守を利用するのもひとつの手です。専門的な知見を持つ保守専門会社にメンテナンスを委託することで、メーカーよりも柔軟な対応が受けられます。
幅広い機種に対応しているため、メーカーによる延長サポートが受けられない製品にも有効です。ただし、場合によっては、部品が確保できなかったり、メーカーによるオフィシャルなサポートが受けられなかったりといったデメリットもあるため、慎重に検討しましょう。
まとめ
サーバーの保守期間は、メーカーからの技術サポートや修理対応が受けられる重要な期限です。保守期間が終了すると、突発的な障害時に迅速な対応が難しくなり、業務に大きな支障をきたすリスクが高まります。そのため、保守期間の終了時期を正確に把握し、必要に応じてリプレースやサードパーティ保守の活用を検討することが大切です。あわせて、管理台帳やメーカー情報をもとに、機器ごとの保守期間を定期的に見直しておくことで、計画的な対応が可能になります。安定したシステム運用を続けるためにも、保守期間の管理と対応策の準備をしっかり行いましょう。本記事が参考になれば幸いです。