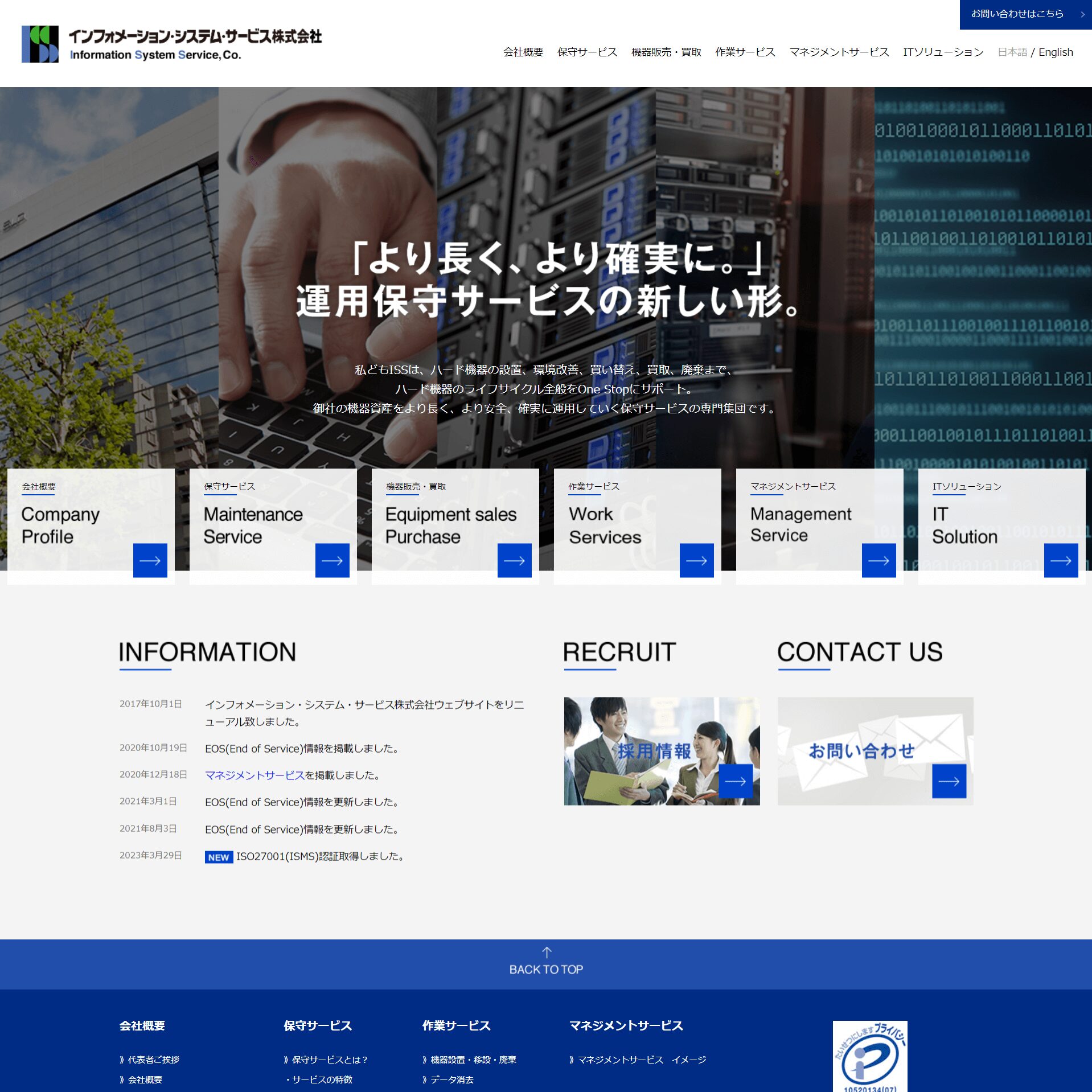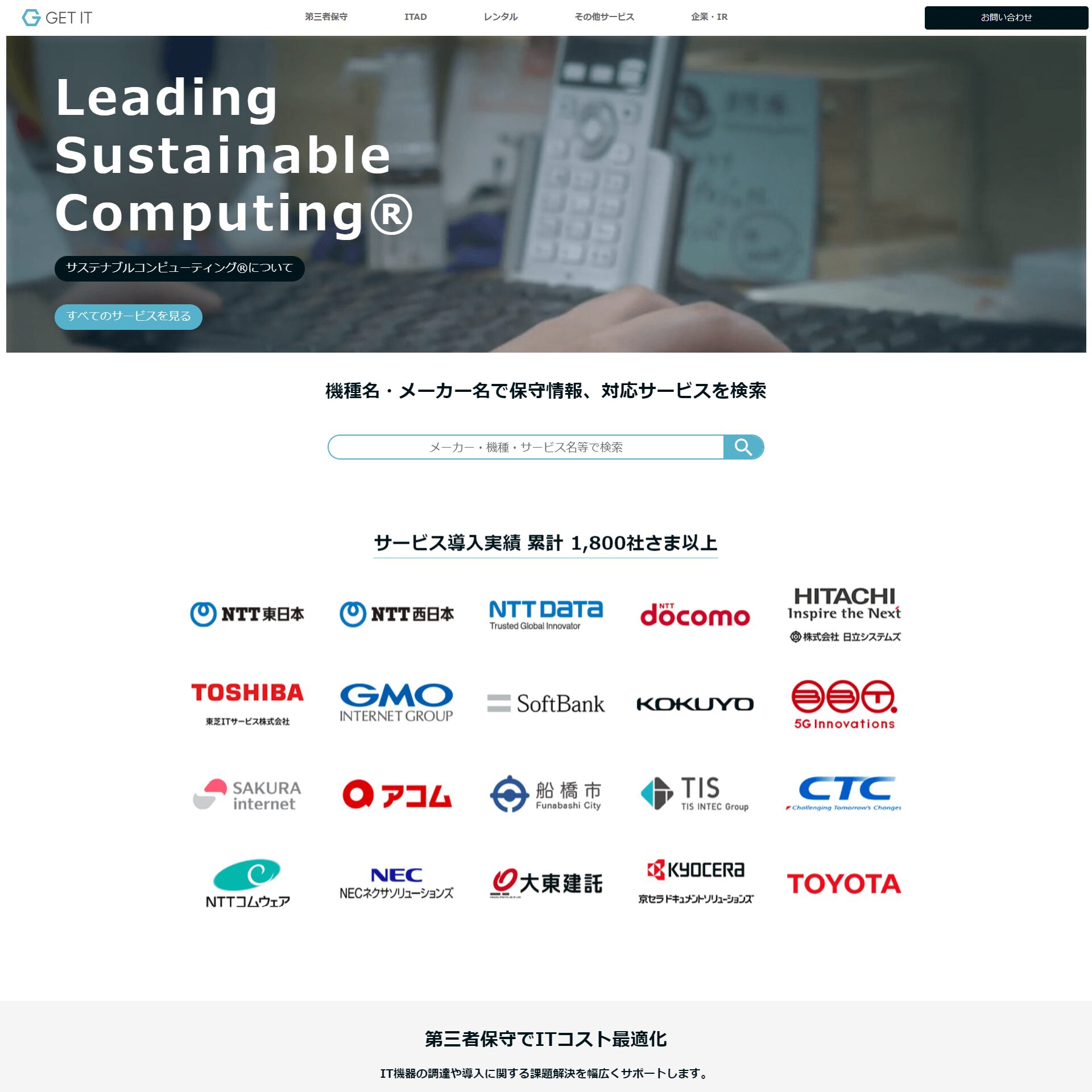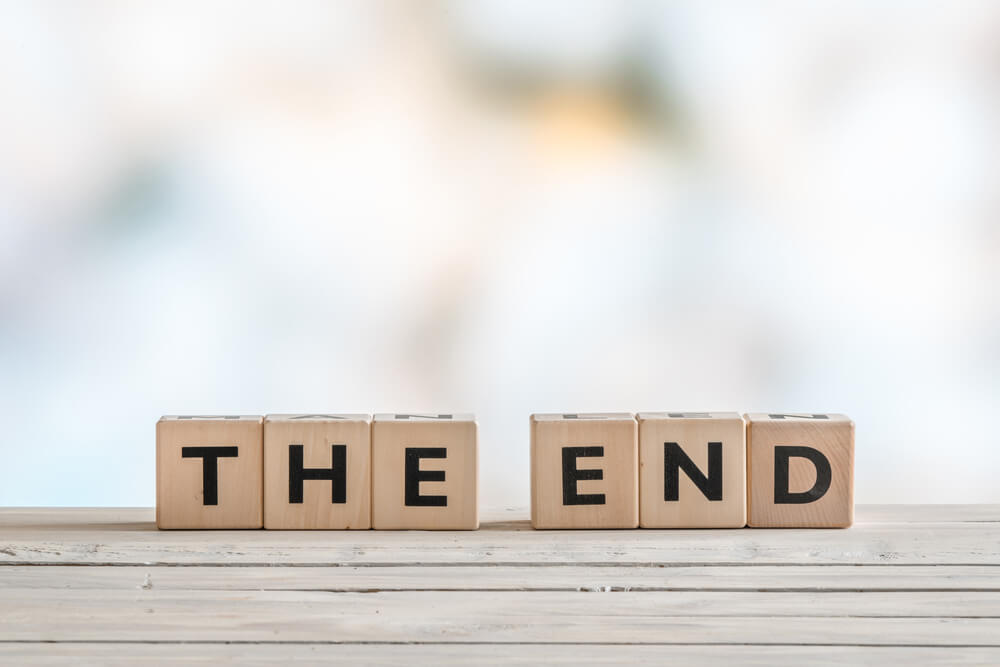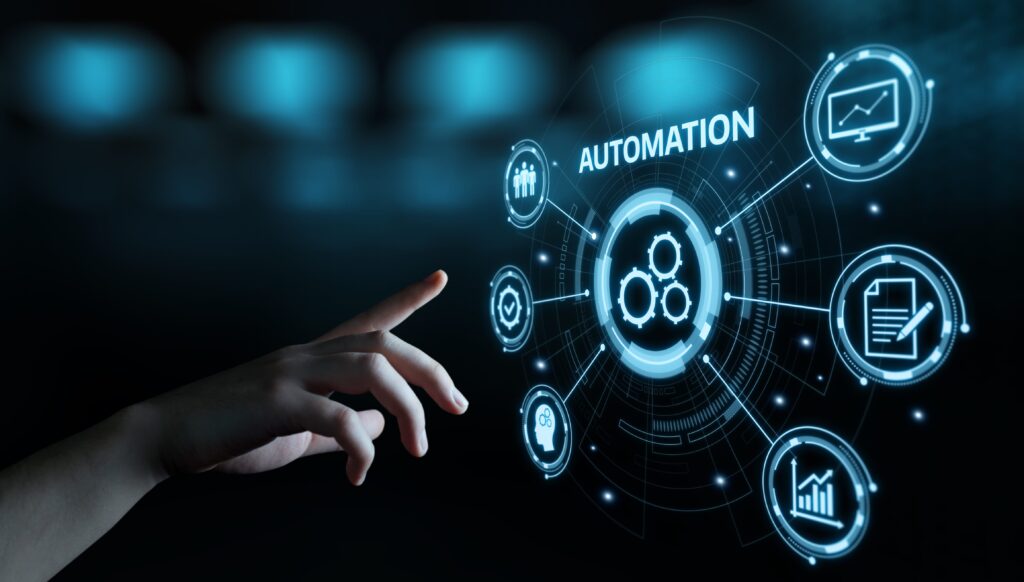IT機器の保守サービスには「メーカー保守」以外に「第三者保守」という選択肢があることをご存じでしょうか。コスト削減やサポート期間の延長など、企業にとって多くのメリットがある一方で、まだ十分に理解されていないのも事実です。この記事では、今さら聞けない「第三者保守」について、基本的な仕組みや特徴をわかりやすく解説します。
メーカー保守終了後も安心!第三者保守の基礎知識
メーカーの保守サポートが終了したIT機器を使い続ける場合、故障時の対応が不安材料になります。そんなときに頼りになるのが「第三者保守」です。以下では、第三者保守の基本的な仕組みや、よく耳にする「EOSL」との関係についてわかりやすく解説します。
第三者保守の仕組み
第三者保守とは、メーカーの保守サポートが終了したIT機器に対して、専門の外部企業が提供する保守サービスのことです。一般的にメーカー保守は製品販売から5年程度で終了しますが、その後も多くの企業では同じ機器を継続して使用しています。ですが、メーカー保守が終了すると、万が一不具合が起きた際に対応してもらえず、業務に支障をきたす恐れがあります。
こうしたリスクを軽減するために、第三者保守が活用されます。第三者保守を利用すれば、故障時の対応や定期メンテナンス、交換部品の提供など、メーカーサポートに準じたサービスを受けられるため、コストを抑えつつ安定した運用が可能になります。
EOSLと第三者保守の関係
EOSLとは「End of Service Life(サービス提供終了)」の略で、メーカーが製品に対する保守サービスを完全に終了するタイミングを指します。これにより、機器に関する修理・部品交換・技術サポートなどが受けられなくなります。
似た言葉に「EOL(End of Life)」や「EOS(End of Support)」がありますが、それぞれ「製品のライフサイクル終了」「サポート終了」を意味しており、どれもメーカーのサービスが段階的に終了していくことを表しています。こうした場面で重要になるのが第三者保守です。メーカー保守が終了しても、第三者企業による支援を受けることで、リスクを抑えて長期間の機器運用が実現できます。
第三者保守を導入するメリットとは?
メーカー保守が終了した機器をどう維持するかは、多くの企業にとって重要な課題です。第三者保守は、そうした課題を解決する有効な選択肢です。以下では、第三者保守を導入することで得られる主な4つのメリットについてわかりやすく紹介します。
EOSL後も安心して使い続けられる
メーカー保守が終了すると、機器の修理や部品の供給が停止し、故障時の対応が困難になります。しかし、第三者保守を活用すれば、EOSL後の機器でも保守サービスを受けることができ、安心して継続利用が可能です。部品の調達から修理対応まで幅広いサポートが用意されており、機器を買い替えずに済みます。
運用コストの圧縮が可能に
第三者保守は、一般的にメーカー保守よりも低コストで提供されることが多いため、保守にかかる年間コストを抑えることが可能です。特に多数の機器を保有している企業にとっては、全体の維持費を大きく削減できる可能性があります。コストパフォーマンスに優れた選択肢として注目されています。
障害の予防でシステムを安定稼働
定期的な点検やメンテナンスを第三者保守サービスに任せることで、機器の異常やトラブルの早期発見が可能になります。障害の発生を未然に防ぐことができるため、業務停止などのリスクも軽減されます。システムの安定稼働に貢献する大きな要素となります。
IT資産の有効活用が可能に
第三者保守によって既存のIT機器を長期間有効活用することで、不要な更新投資を抑えることが可能です。その結果、限られた予算を新規システムや戦略的なIT投資にあてやすくなり、資産の最適化が図れます。長期的に見て柔軟なIT戦略を実現するための基盤となるのが第三者保守です。
第三者保守で後悔しないためのチェックポイント
第三者保守はコスト削減や機器の延命に有効な手段ですが、導入前に注意すべきポイントも存在します。以下では、第三者保守を選ぶ際に気をつけたい重要な点を紹介します。
必要な保守部品を確保できるか確認を
第三者保守を導入する際は、自社で使用している機器やシステムに必要な保守部品が確実に入手できるかを事前に確認しましょう。とくに古い機種や海外製品の場合、部品の流通量が限られていることもあり、調達が難航することがあります。万が一、故障時に必要な部品が入手できなければ、機器の修理ができず、業務に支障をきたす可能性も否定できません。保守業者に在庫状況や調達ルートを確認し、安定的な供給が見込めるかを見極めることが重要です。
保守対応の体制やスピードを見極める
第三者保守を依頼する際には、保守会社の対応体制についても詳細に確認しておきましょう。障害発生時に、どれだけ早く対応スタッフが駆けつけてくれるのか、対応時間帯やサポート窓口の体制はどうなっているのかは重要な判断材料です。また、24時間365日の対応が可能かどうかや、修理完了までの標準的な時間も事前に把握しておくことで、緊急時のトラブル対応に安心感をもてます。サービスレベル(SLA)の内容をよく確認することが肝心です。
まとめ
第三者保守は、メーカー保守終了後もIT機器を安心して使い続けるための有効な選択肢です。コスト削減や安定稼働といったメリットがある一方で、導入前には部品調達の可否やサポート体制の確認が欠かせません。第三者保守を正しく理解し、自社に合ったサービスを選ぶことで、IT資産の有効活用と業務の安定運用を実現できるでしょう。